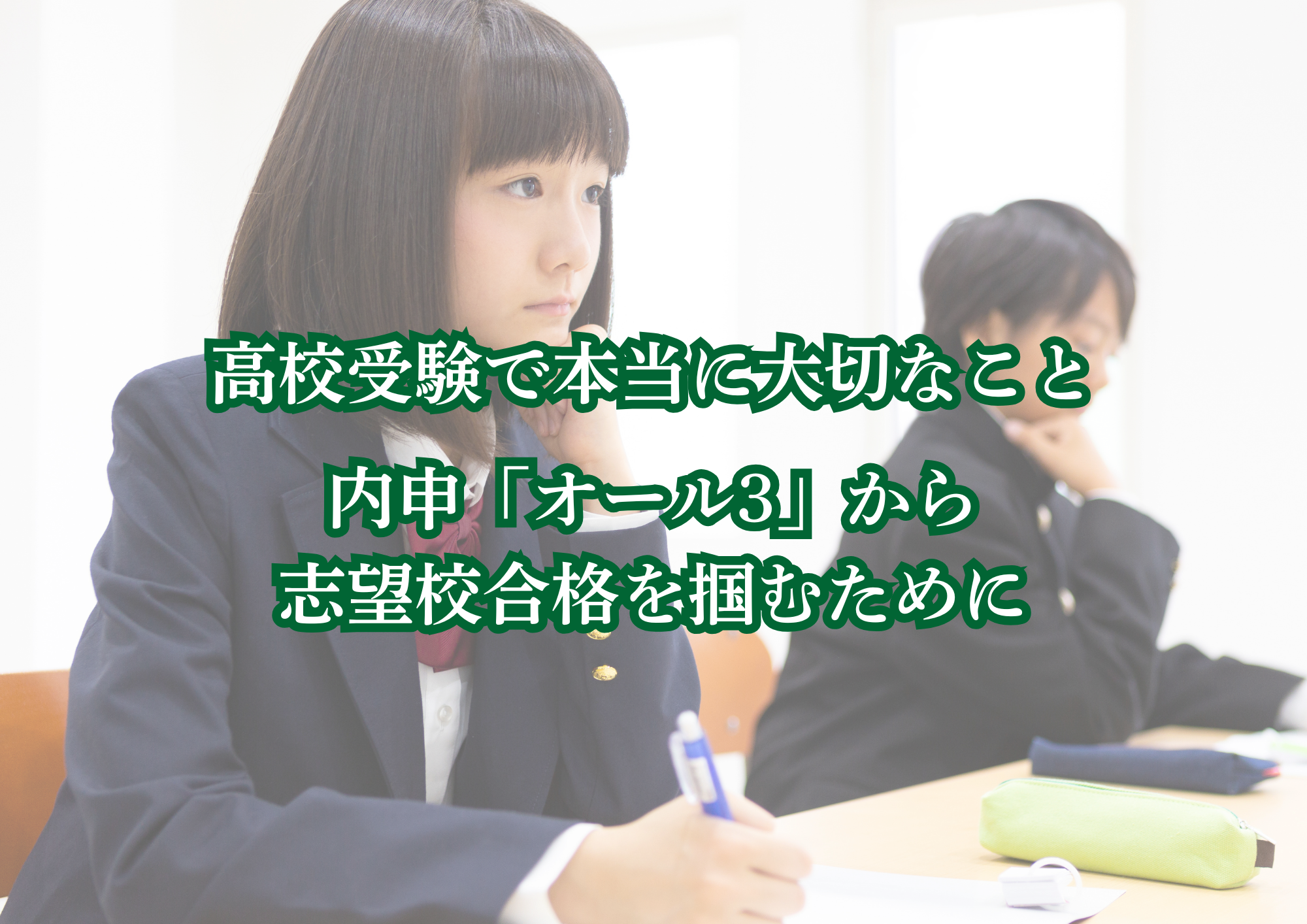「内申がオール3。これは平均だから大丈夫でしょうか?」
この質問、毎年たくさんの保護者の方からいただきます。
実は“オール3”という言葉ほど、あいまいな評価はありません。
なぜなら、内申点は学校や学年の平均点、テストの難易度によって大きく変わるからです。
「内申3=平均」とは限らない理由
一般的に「通知表の3」は平均的な印象がありますが、実際にはそうとは限りません。
たとえば、テストが簡単な学校では平均点が高くなり、3を取るための基準も上がります。
その結果、内申3を取る=実際のテストでは上位層というケースも多くあります。
一方で、難易度の高い学校では、テストで努力しても2や3になることもあります。
つまり、内申の数字だけでは実力を測れないのです。
「オール3」だと受験できる高校が限られる現実
川崎・神奈川エリアの高校受験を例にすると、
- オール3〜4 → 公立でいえば新城高校や橘高校あたりが目安
- オール4〜5 → 多摩高校、川和高校などの上位校
といったイメージになります(あくまで目安です)。
そして、オール3では私立併願の確保が難しいケースもあります。
私立を併願できないと、公立出願の際にレベルを下げざるを得ないため、第一志望に挑戦できないことが起こります。
さらに、近年では公立高校の二次選考でも内申点が加味されるようになり、
以前よりも内申の影響力が大きくなっています。
高校受験の本質は「内申」と「本番点」の両立
高校受験で求められるのは、
「内申をきちんと取りながら、本番でも点数を取ること」
この2つを両立できるかどうかが、合否を分けます。
「定期テストさえ取れれば大丈夫」と思っている方も多いですが、
その“取る”が難しいのです。
定期テストで伸びない生徒の共通点と解決策
1.全範囲を本当に勉強していない
5教科+副教科(特に中2・中3)は全範囲を網羅できていないことがほとんどです。
やっていない範囲は当然解けません。
対策:試験範囲をリスト化し、提出物・ワーク・プリントを最低2周、基本問題を3周。
たったこれだけで点数は安定して上がります。
2.「見ないと解けない」状態のまま終えている
勉強しても本番で解けないのは、「見ないで解ける」まで仕上がっていないからです。
対策:「何も見ずに解く→採点→やり直し」の反復。
普段の正答率×0.8が本番点の目安になります。数値で管理しましょう。
3.丸暗記で“理解”が伴っていない
問題の意味を理解せずに覚えるだけだと、少し聞き方が変わるだけで解けなくなります。
対策:間違えた問題は「なぜ間違えたか」を書き残す。
自分の言葉で説明できるようになれば、確実に点は伸びます。
週1・2回の個別だけでは限界がある理由
個別指導は柔軟ですが、学習量が圧倒的に足りないことが多いです。
週1〜2回の授業だけで成績を上げるのは現実的ではありません。
みやうち塾では、この課題を解決するために
以下のような体制で「結果を出す仕組み」をつくっています。
1.1人の講師が5教科を横断指導
教科ごとに講師が変わらないため、全体のバランスを見ながら指導します。
たとえば、テスト前は理科・社会に集中、普段は英語・数学を中心にするなど、
科目配分を最適化します。
2.通い放題で「量」を確保
週4回以上が基本。
勉強は“やった量”が成績を決めます。
塾にいる時間を最大化し、試験範囲を全て終わらせるまでやり切るのがみやうち塾の方針です。
(週1・2回だけ希望の方は、別のスタイルの塾をおすすめします)
3.進捗を数値で管理
・範囲達成率
・ブラインド正答率(見ずに解けた率)
・直し完了率
これらを数字で可視化し、「当日の点数を予測できる学習」を行います。
テストは“受けに行くだけ”の状態を作るのが目標です。
志望校別の基本方針(目安)
- 偏差値40台 → 住吉高校・高津高校ライン:副教科で差をつける+国英の文章題強化
- オール3〜4 → 新城・橘ライン:主要5教科の安定+内申の底上げ
- オール4〜5 → 多摩・川和ライン:記述力・資料読解・長文演習を高精度化
(※あくまで目安です。学校や年度によって異なります)
高校受験を成功させる3ステップ
-
全教科・全範囲をやり切る(副教科も含む)
-
見ないで解ける状態にする(×0.8で本番点を予測)
-
丸暗記ではなく理解+言語化(間違い直しノートで習慣化)
「毎日塾を開ける」ことが、結果を生む理由
みやうち塾は、とにかく勉強時間で差をつける塾です。
勉強は「質+量」で決まりますが、まず量がなければ質も育ちません。
塾を毎日開け、疲れ果てるまで頑張る生徒を全力で応援します。
人生で一度きりの高校受験。
目標をあきらめる前に、「やり切った」と言える時間を過ごしましょう。